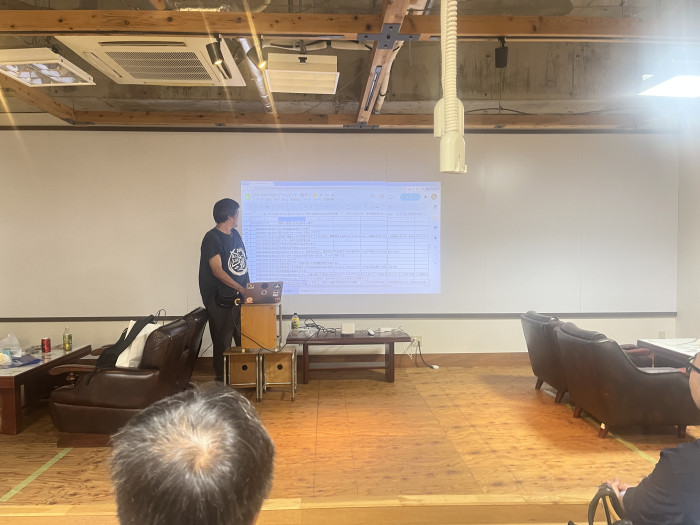

下流での被害や防災の共有が課題
→ 「どちらに流れるか」「誰が情報を持つか」を共有する必要
→ 防災情報の連携が鍵
■ 防災連携のポイント:「町内で共有する方法」や「インフラとの連携」が重要
同じテーブルに防災士さんもいらしていて、事前に防ぐにはどうしたらいいかという視点でも話ができました。
防災無線があるものの、今回の短時間の大雨のときはアナウンスが聞こえづらかったこともあり、近隣とのネットワーク・連携が鍵となってくるのでした。
■ 今後のアクションとして
オープンデータ×支援マップ→ 誰でも使える地域防災マップを作るアイデア
地域の人との勉強会を実施→ 現場の声を集めて改善点を共有
避難所と心の安心をセットで考える→ 助け合いを感じられる場所づくり
など話し合いました。
Code for Kanazawa Civic Hack Night Vol.87 (2025/11/13 19:00〜)
# Civic Hack Night Kanazawa 初めての方も大歓迎です。 解決して欲しい地域課題をお持ちの方、技術を用いて課題解決したいエンジニアの方、そういったことに興味がある企業の方々、自治体、大学、どなたでも参加できますよ! # イベント概要 【重要】出張シビックハックナイト!今回は場所が変わります!ご注意ください。 本会は、原則毎月第2木曜日に開催される誰でも参加可能な無料イベントで、エンジニアやデザイナーはもちろん、行政職員の方、地域課題に興味がある方、主婦、学生など、広く市民の方が集まって地域課題やシビックテックについての議論やものづくりを行う場です。 基本...
https://cfk.connpass.com/event/373819/















